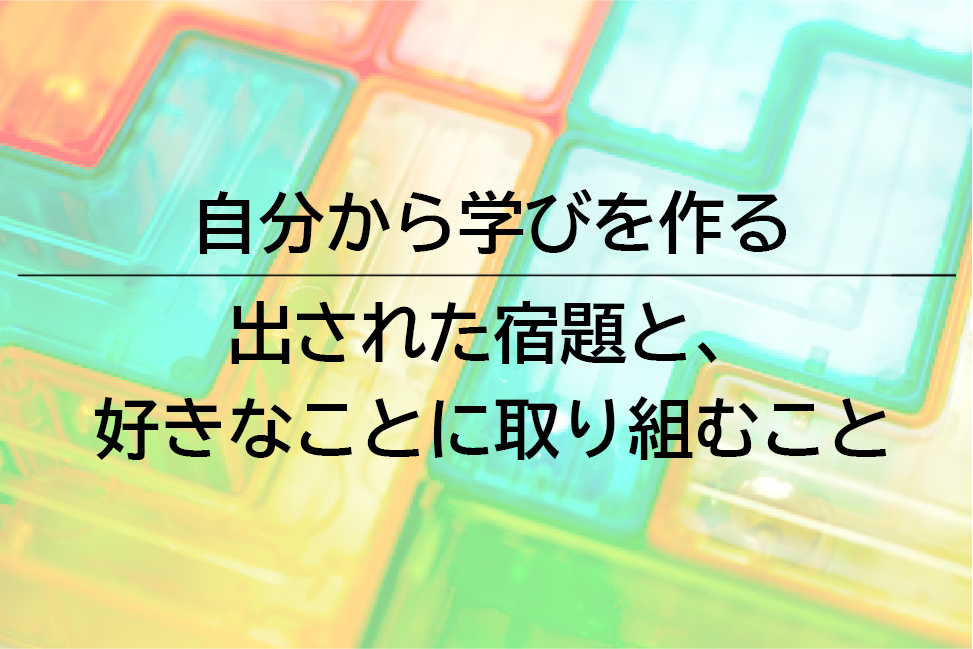自分から学びを作る ― 出された宿題と、好きなことに取り組むこと ―
ダンスのレッスンは欠かさずに通う、早朝から野球の練習には取り組むけれど、学校の宿題はできない、という子供がいるといいます。学校の授業と関連した宿題には関心が向かないことが多く、特に学んだことを身につけるための復習や練習問題、ドリルなどは先生から課せられるという外側からの圧力を感じる(外発(がいはつ)的動機づけ)ため、負担に感じてしまうのです。自分からやりたい活動は、その学ぶ内容が動機の元になる(内発(ないはつ)的動機づけ)ため、少しぐらいつらいことでも取り組もうとします。
一方で、学校の宿題にいくらか前向きに取り組む子供もいて、その場合の動機は、テストがあるからとか、できないとはずかしいからというような、みんなと違うことに不安を感じて取り組む場合と、自分にとって将来に役立つからとか、努力することが大事だから取り組むという場合があります。これらは、好きだから取り組む内発的な動機ではなく、いずれも外発的な動機ですが、実際に取り組めば、それだけ学習したことの定着は進みます。マレーシアでは保護者の教育熱が高いこともあり、何かしらの学習活動を、放課後に取り組む子供が多いそうです。自分から学ぶという習慣が育っていて、特に英語の習得は、国の方針もあり積極的に学んでいます。
また、熱中するものがないという子供には、内発的な動機が生まれないのかというと、そうでもありません。ときどき、授業の中でおもしろいと感じたり、家に帰っても学校で習った歌を歌っていたりする場合は、先生の話や教科書の内容に引きつけられた動機が、子供の内側に芽生えたときです。この場合は、関心のない教科の内容に比べて、記憶に残ったり成績がよかったりするものです。
もう一つ、習い事やスポーツ活動、それに地域の様々な活動には、授業だけでは身につかない、ねばり強さ、考え抜く力、役割を理解して果たす力、自分から相手に依頼する力などの、学んだ様々なことを活用する力(資質や能力)を育てる場面が多くあります。学校以外の時間で好きなことに取り組むことは、宿題で得られる能力とは異なる能力を育てる時間であり、これらの活動が、様々な能力につながると気づくことができれば、学びに向かう一つの動機になるかもしれません。