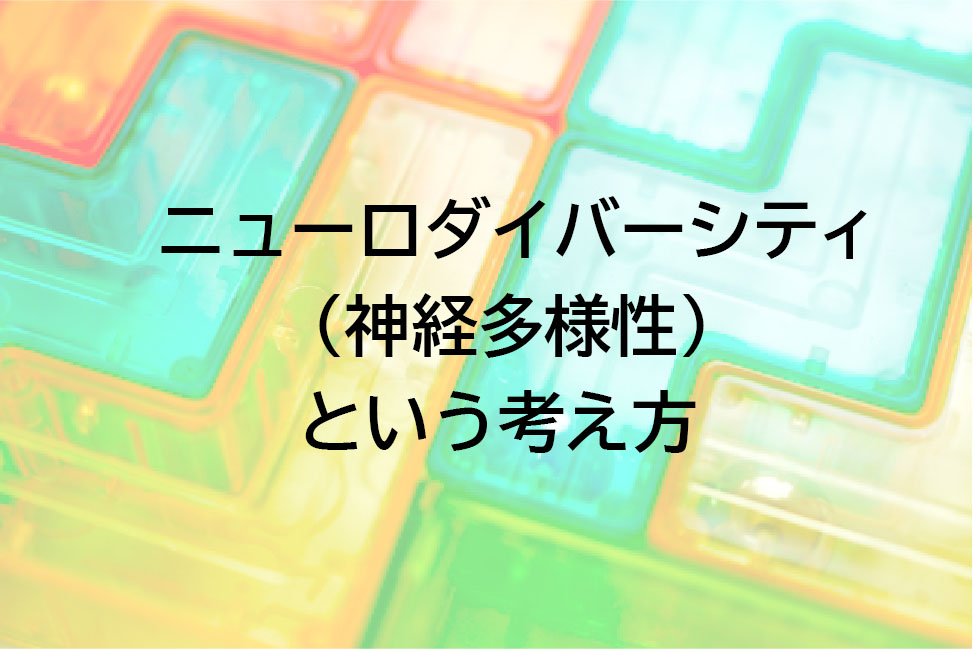ニューロダイバーシティ(神経多様性)という考え方
◯多様性を尊重する教育への変化
近年、多様性を尊重する社会への動きが進み、学校教育の現場でも「学習の個性化」や「指導の個別化」など、子供たち一人一人の特性を尊重した授業が広がっています。令和5年6月に閣議決定された新たな教育振興基本計画にも、「支援を必要とする子供の長所・強みに着目する視点の重視、地域社会の国際化への対応、多様性、公平・公正、包摂性(DE&I)ある共生社会の実現に向けた教育を推進」と明記されています。
◯ニューロダイバーシティとは
ニューロダイバーシティ(神経多様性)とは、ニューロ(脳・神経)とダイバーシティ(多様性)という2つの言葉が組み合わされて生まれた言葉です。この考えは、発達障害の当事者によって提唱された考え方です。人には得意不得意があるということを理解するとともに、それを多様性の見え方の一つとして考えるものです。苦手なことがあると生活に支障をきたすこともありますが、そうした困難も人間の多様性の一部と捉え、互いに支え合って生きていこうというのが、ニューロダイバーシティの考え方です。
◯私たちの日常から考える多様性
私たちは誰しも、「得意なこと」もあれば「苦手なこと」もあります。「ピアノをひくのが好き」「本を読んでいる時間が幸せ」「ゲームなら負けない」もあれば、「漢字は嫌」「まぶしい場所は疲れる」「競争したくない」だってあります。一人一人が、たくさんの「得意」や「苦手」を持っていて、それら一つ一つの程度や広がりにも違いがあることで、誰でもない「自分」という存在になっています。それぞれが「自分」の力を発揮しながら、互いの「得意」や「苦手」を認め合っていくことで、誰もが「自分らしく」いられます。
◯社会での支え合い
大人になっても、それぞれの特性に応じて仕事や日常生活で活躍したり、時には助けを借りたりしながら生きていきます。例えば、書類作成が苦手な人は同僚にチェックをお願いし、逆に自分の得意な分野で周囲をサポートするといった相互援助が社会では当たり前に行われています。ニューロダイバーシティは、このような一人一人の特性を「障害」として否定的に捉えるのではなく、人にはそれぞれ異なる特性があるという前提に立ち、お互いを理解し、支え合いながら共に生きる社会を目指す考え方です。
◯子供たちの学びを支える環境づくり
小学4年生の山田くんは文字を書くことに困難があって、書いて考えをまとめたり、伝え合ったり評価を受けたりという体験ができない中で、学習への意欲を失っていました。タブレットを使って、書く活動を入力で補えるようになったことで、参加できる授業場面が増えています。特に、今までは観察の記録ができず、興味があるのに投げやりになりがちだった理科の授業では、写真や気づいたことのメモを元に意欲的に発言し、自信をつけたようすが伺えました。学校では、そんな山田くんに対して、学習場面に応じて方法を選択できるようにするといった動きもあり、理解が広がっています。このように、子供たちの学びの中でのつまずきや困難を、「できない」と「子供の側の問題」として評価するのではなく、その子の学びやすさを探って「方法」の選択肢を増やしたり、そうしたさまざまな学習へのアクセスの方法があることを認め合ったりできる環境があることが大切です。
一人一人の違いを認め合い、互いの長所を活かせる関係づくりが、これからの共生社会につながっていくのです。